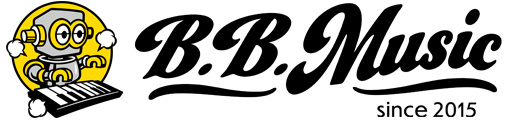電子ピアノにはあえて「ノイズ」が入っている
電子ピアノの進化は、単に音を出すだけでなく、アコースティックピアノが持つ微細なニュアンスや響きまでも再現することに注力してきました。その象徴的な技術の一つが「ダンパーノイズ」です。本記事では、このダンパーノイズの概念から、主要メーカーであるヤマハ、ローランド、カワイがどのようにこの音響要素を追求してきたのかを、具体的な機種や歴史的背景を交えながら深掘りします。

ダンパーノイズとは何か?
ダンパーノイズとは、アコースティックピアノにおいて、ダンパーペダル(右側のペダル)を踏み込んだり離したりする際に生じる微細な機械的な音のことです。
通常、ピアノの弦はダンパーによって振動を止められていますが、ペダルを踏むことでそのダンパーが弦から一斉に離れます。そのときに生じる「シャーン」というわずかな金属的ノイズ。これこそが、ピアノの“生っぽさ”を感じさせる自然な音響の一部なのです。
電子ピアノでは、このダンパーノイズを再現することで、アコースティックピアノの臨場感をよりリアルに感じさせる工夫がされています。さらに、最近の機種では、ペダルを踏む速度や深さに応じてノイズの音量や音色が変化するモデルもあり、より細やかな表現が可能になっています。
「ノイズ」は本当に必要なのか?
「リアリティのためとはいえ、ノイズは邪魔では?」と感じる方もいるかもしれません。しかし、アコースティックピアノに慣れ親しんでいる演奏者にとって、これらのノイズは「空気感」や「タッチの感触」を伝える重要な要素です。
電子ピアノの開発者たちは、ただクリアな音を出すだけでなく、アコースティックピアノにしかない“雑味”までも再現することで、より豊かで自然な演奏体験を提供しようとしているのです。
主要メーカーにおけるダンパーノイズの追求
ダンパーノイズの再現は、各電子ピアノメーカーがアコースティックピアノのリアリティを追求する過程で、独自の技術と哲学をもって取り組んできた領域です。特定の「最初の機種」を断定することは困難ですが、各社の音源技術の進化と密接に結びついています。
1. ヤマハ(Yamaha):VRMによる共鳴再現の深化
ヤマハは、世界的なアコースティックピアノメーカーとしてのノウハウを活かし、電子ピアノ「Clavinova(クラビノーバ)」シリーズで、アコースティックピアノの響きを忠実に再現する技術を追求してきました。
ダンパーノイズを含むペダル操作時の微細な響きの再現に大きく貢献しているのが、ヤマハ独自の「VRM(Virtual Resonance Modeling)」技術です。VRMは、弦の共鳴やダンパーの共鳴、さらには響板の響きといった、アコースティックピアノ特有の複雑な共鳴現象を物理モデルによってシミュレートする画期的な技術です。
- 歴史と搭載機種: VRMは、おおよそ2014年頃に登場したClavinova CLP-500シリーズから導入され始めました。この世代から、ダンパーペダルを踏み込んだ際の共鳴の豊かさや、ダンパーノイズのリアルさが飛躍的に向上しました。
- 特に、CLP-600シリーズ(2017年頃~)や、現在の主力モデルであるCLP-700シリーズ(2020年頃~)では、VRMがさらに進化し、ダンパーノイズを含むよりきめ細やかなアコースティックピアノの響きが再現されています。CLP-700シリーズでは、ダンパーノイズの音量調整も細かく行えるようになり、よりユーザーの好みに合わせた設定が可能になっています。
2. ローランド(Roland):スーパーナチュラル・ピアノ音源による表現力
ローランドは、サンプリングとモデリングを融合させた独自の「スーパーナチュラル・ピアノ音源」によって、アコースティックピアノの演奏表現をデジタルで再現することに注力してきました。
スーパーナチュラル・ピアノ音源は、従来の単純なサンプリング音源とは異なり、音の発生から減衰、そして音量・音色の変化を物理モデルによってシミュレートします。これにより、単にダンパーの音をサンプリングするだけでなく、ペダルの踏み込み具合やタイミングに応じたダンパーの動作、それに伴うノイズや共鳴まで、よりダイナミックかつリアルに再現することが可能になりました。
- 歴史と搭載機種: スーパーナチュラル・ピアノ音源は、おおよそ2009年頃に登場したHP-307などのデジタルピアノに初めて搭載されました。
- これ以降のFPシリーズ、HPシリーズ、LXシリーズといったローランドの主要な電子ピアノには、このスーパーナチュラル・ピアノ音源が搭載されており、ダンパーノイズの再現性も高い水準で実現されています。最新のLX700シリーズやHP700シリーズでは、さらに進化した音源とスピーカーシステムにより、ダンパーノイズを含むアコースティックピアノの響きを非常に自然に再現しています。多くの機種で、メニュー画面の「ピアノデザイナー」や「音源設定」などから、ダンパーノイズの音量や特性を調整できる機能が備わっています。
3. カワイ(Kawai):バーチャル・テクニシャンによる詳細な調整
カワイは、世界有数のアコースティックピアノメーカーとしての背景を持ち、そのサウンドをデジタルピアノ「CAシリーズ」「CNシリーズ」などで忠実に再現することを目指しています。
カワイのデジタルピアノにおけるダンパーノイズの再現は、独自の音源技術に加え、「Virtual Technician」機能と深く関連しています。バーチャル・テクニシャンは、アコースティックピアノの調律師が行うような、ハンマーの硬さや響板の特性、そしてダンパーノイズといった様々な音響要素をデジタル上で細かく調整できる画期的な機能です。
- 歴史と搭載機種: カワイのデジタルピアノにおいて、ダンパーノイズが明確な調整項目として「バーチャル・テクニシャン」内に組み込まれたのは、おおよそ2010年代前半以降の比較的新しいモデルからと考えられます。
- カワイの公式情報や専用アプリの互換性情報によると、CAシリーズ(CA17, CA48, CA58, CA67, CA97など、そして現行のCA401/501/701/901など)やCNシリーズ(CN14, CN17, CN25, CN27, CN29, CN35, CN37, CN39など、そして現行のCN201/301)といった多くのデジタルピアノで、バーチャル・テクニシャン機能が搭載されており、その中に「ダンパーノイズ」の調整項目が含まれています。
- これらのモデルでは、カワイ独自の「ハーモニック・イメージング(Harmonic Imaging)」音源や、より進化した「プログレッシブ・ハーモニック・イメージング(Progressive Harmonic Imaging)」、そして現行の最上位音源である「SK-EXレンダリング音源」を搭載しており、バーチャル・テクニシャン機能を通じてダンパーノイズの音量や特性を細かく設定できます。特に、ペダルを踏み込む速度や離す速度に応じてノイズの表現が変わる点も再現されており、高い表現力を実現しています。
ダンパーノイズの設定方法
ダンパーノイズの設定方法は、メーカーや機種によって異なりますが、一般的には以下のいずれかの方法で調整できます。
- 本体のメニュー画面からの設定:
- ヤマハ
「PIANO ROOM」→「VRM」でダンパーノイズの設定ができます。 - ローランド
「ピアノデザイナー」→「ピアノ音色の設定」からダンパーノイズの設定ができます。 - カワイ
「セッティングメニュー」からダンパーノイズを設定できます。
- ヤマハ
- 専用アプリからの設定:
- 近年では、スマートフォンやタブレットと連携できる専用アプリを提供しているメーカーも多く、アプリを通じてより直感的にダンパーノイズのオン/オフや音量調整が行える機種もあります(例:ヤマハ「Smart Pianist」、ローランド「Piano Every Day」、カワイ「PianoRemote」など)。
設定時の注意点:
- 音量レベルの調整: ダンパーノイズは、あくまでアコースティックピアノのリアルな響きを再現するための「付加要素」です。ノイズが大きすぎると演奏の邪魔になる場合もありますので、ご自身の演奏環境や好みに合わせて音量レベルを調整することをおすすめします。
まとめ
ダンパーノイズは、電子ピアノがアコースティックピアノの持つ微細な音響特性を再現し、より豊かな演奏体験を提供するための重要な技術です。各メーカーの独自の技術の進化によって、このダンパーノイズの再現性は年々高まっており、デジタルでありながらもアコースティックピアノの魂を感じさせる演奏が可能になっています。ぜひご自身の電子ピアノで、この深みのある響きを体験してみてください。
取扱の電子ピアノはこちら